みなさんは、振休と代休の違いをご存知でしょうか。
正確に理解し運用している人事労務担当の方もいますが、中には「正直、明確な違いがわからず会社の慣習のまま運用している」という方もいるかもしれません。
しかし、その「なんとなく振休代休を運用している」状態は、コンプライアンス上非常に危険です。
もし曖昧な理解のまま運用すれば、気付かないうちに法令違反に加担し、会社に損失を与える可能性もあります。
自分が担当する以上、会社に損害を与える行動は避けたいですよね。
そこでこの記事では、振休と代休の違いを詳しく紹介します。
また、分かりにくい運用上の注意点と、実際のトラブル事例・判例も解説しましょう。
この記事を読めば、振休・代休の違いを正しく理解し、正確な運用ができますよ。
「振休・代休の違いを理解したい」「一応理解してるけど、改めて学び直したい」という方は、ぜひ最後まで読んでください。
そもそも振休・代休とは

企業は法律上、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労働基準法35条)。
そこで、休日出勤を命じる際には振替休日(振休)または代休を利用し、別日に休日を与える必要があります。
人事労務担当者の方の中には、振休と代休に関して「厳密な意味まで理解できていない」という方も、いるかもしれません。
そこで、まずは振休・代休とは何か解説しましょう。
- 振休:事前に休日と定められていた日を労働日とし、かわりに他の労働日を休日とすること
- 代休:休日労働を行なった事後に、代償として以後の特定の労働日を休みとするもの
参照:厚労省『振替休日と代休の違いは何か。』
基本的な違いは、事前に休日労働・振替休日を決めているかどうかです。
ただし、振休・代休の間にはそれ以外にも細かな違いが存在します。
詳細な違いはこの後説明しますので、まずは基本的な語句の意味を理解しましょう。
振休・代休の違い
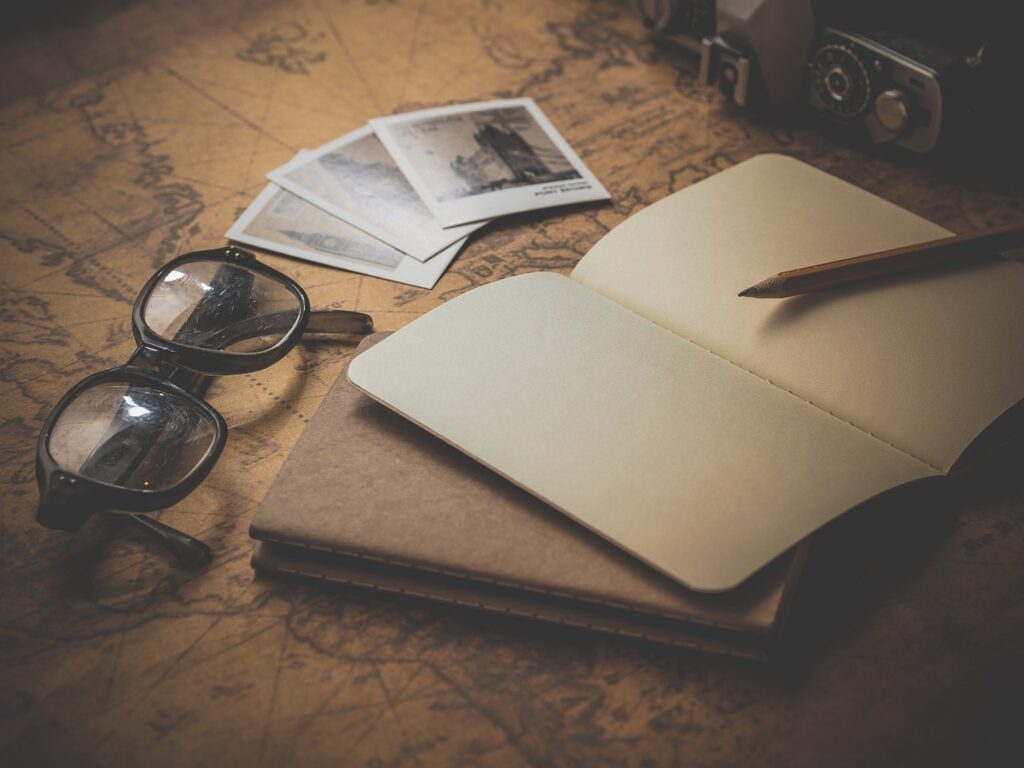
振休・代休の意味を理解いただいたところで、さらに詳しく違いを解説しましょう。
振休・代休の違いは、大きく分けて以下の2点です。
- 「事前申請か事後申請か」
- 「割増賃金の有無」
実際の運用に関わる部分なので、ひとつづつ確認していきましょう。
事前申請か事後申請か
振休・代休の意味を確認した際にもお話ししたとおり、まずは事前申請か事後申請かで扱いが変わります。
・振休:事前申請
・代休:事後申請
振休は、事前に通常出勤日と休日を入れ替えて働くことを決めている状態をいい、一方代休は休日労働の後に代わりの休日及び割増賃金を与えることを言います。
もし振休扱いで従業員に休日労働を命じるつもりだったとしても、休日労働後に休みを付与した場合は、前もって振り替えていないため代休扱いになります。
割増賃金の有無
もうひとつ大きな違いは、法定休日の労働に対して、割増賃金の支払い義務が生じるか否かです。
覚えていただきたいのが、法定休日に出勤し代休を取得した場合は、従業員に対し35%の割増賃金を支払う必要があることです。
例えば、時給2,000円の従業員が法定休日に7時間労働した場合、以下の計算式になります。
- 代休の場合:2,000円 × 135% × 7時間 = 18,900円
振休と比べ35%増しの賃金を支払うことになるため、振休と代休を勘違いして与えないよう、注意しましょう。
ちなみに、法定外休日の場合は規定の労働時間内に収まれば、割増賃金は発生しません。
取得義務があるかどうか
振休は休日出勤後に必ず代わりの休みを取得させる義務がありますが、代休は休日の取得義務がありません。
なぜなら、法律上、代休は割増賃金の支払いで足りるとされているからです。
一方、会社の就業規則で休日を取得しなければならない旨が記載されている場合は、必ず休日を与えなければいけません。
振休・代休の運用上の注意点5つ

振休・代休の意味と違いは、理解できましたでしょうか。
前述の通り、振休と代休は注意して運用しないと、想定していない割増賃金を支払う場合もあります。
実はその他にも、運用上の注意点が5つ存在します。
- 振休は就業規則に記載する
- 取得期限は共に最長2年
- 事後申請は代休扱いになる
- 代休は割増賃金が発生する場合がある
- 休日出勤は36協定の締結と届出が必要
後からミスに気づいて「知らなかった」では済まされないので、丁寧に確認しましょう。
振休は就業規則に記載する
振休を自分の会社に導入する場合は、事前に就業規則へ記載する必要があります。
振休は使用者(企業)と労働者の間で交わされる、就業規則や職務規則の規定に則って運用されなければいけません。
なので、事前に就業規則に法定休日を他の労働日と入れ替える場合がある旨が記載されているか、確認しておきましょう。
他方で、記載がない場合も労働者と個別で合意を取れていれば、振休を与えることは問題になりません。
取得期限は共に最長2年
振休・代休の取得期限は、共に最長2年とされています。
実は振休・代休共に、労働基準法上で取得期限自体は記載されていません。
ただし、同法115条「賃金その他の請求権の時効」が適用され、2年間で振休・代休を取得する期限は消滅すると考えられています。
一方「法律上問題ないなら取得期限は無期限でいいだろう」と思い、就業規則上で期限を設定しないでおくと、のちに問題になる可能性が高いです。
長時間労働や未払い賃金の発生にもつながるため、トラブル防止のためにも数ヶ月以内に取得するよう記載しておきましょう。
事後申請は代休扱いになる
「代休は割増賃金が発生するから、振休扱いにしたい」と思っても、すでに労働者が休日出勤している場合は、代休扱いになります。
ミスを起こさないためには、どの休日と勤務日を交換するか、休日出勤前に決めておくことが大事です。
また割増賃金を免れる目的で、代休を振替休日として不正に扱うと、未払い賃金の支払いを求められる場合があります。
支払う賃金が大きく変わるため、会社は振休と代休の違いを正しく把握し、運用するように心がけましょう。
代休は割増賃金が発生する場合がある
代休は割増賃金が発生する場合があるため、注意が必要です。
一方で、どの休日でも確実に割増賃金が発生するわけではありません。
法定休日に出勤を命じた場合は割増賃金が発生し、法定外休日に出勤した場合は、1日8時間または週40時間の労働時間を過ぎた場合、割増賃金が発生します。
就業規則で法定休日が何曜日か特定されていない場合は、判例・通説上、土曜日が法定休日とされることが多いです。
ちなみに振休であっても、週をまたがって休日を振り替えると割増賃金が発生します。
振休は必ず同一週内に振り返るように、注意しましょう。
休日出勤は36協定の締結と届出が必要
法定休日に出勤させる場合は、事前に36協定を締結していることが条件です。
36協定とは、労働基準法第36条の「時間外労働や休日出勤に関する規定」に則った協定のこと。
36協定の中に先ほど解説した、法定休日の出勤に関する割増賃金規定や、振替休日に関する規定が集約されています。
なので、休日出勤や振替休日を行う予定がある場合は、事前に必ず36協定を使用者と労働組合や労働者代表の間で締結しましょう。
また、36協定は所定の書面で作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
振休・代休に関するトラブル事例

振休・代休の違いや、運用上の注意点は理解できましたでしょうか。
振休・代休は使用者側も労働者側も明確に違いを理解していない場合も多いため、過去にトラブルも発生しています。
会社でトラブルを起こさないためにも、振休・代休に関するトラブル事例を3つ紹介しましょう。
- 振休取得中に法定労働時間を超えた
- 管理職なのに振休を与えた
- 従業員が欠勤時に無断で代休を振休処理にした
振休取得中に法定労働時間を超えた
法定休日出勤でも割増賃金の支払いを免れる振休ですが、法定労働時間を超えた場合は、割増賃金が発生します。
例として、下記の場合は法定休日・法定外休日を問わず、振休でも割増賃金が発生します。
【割増賃金の発生例】
- 休日に9:00-20:00(うち1時間休憩)まで労働した
→1日の労働時間は10時間なので、8時間を超えた2時間分に対し25%の割増賃金が発生する
たとえ振休を与えたとしても、1日8時間・週40時間を超える場合は、25%の割増賃金が発生することを覚えておきましょう。
管理監督者なのに振休・代休を与えた
一般労働者ではなく、管理監督者にも関わらず振休・代休を与えることは、トラブルに繋がります。
そもそも管理監督者は基本的に36協定の適用外で、時間外労働や休日出勤に関する規定が適用されません。
そのため、使用者は管理監督者に振休・代休を与える義務がありません。
一方で、管理職なら全員管理監督者に当たるわけではなく、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみ適用外になります。
管理監督者の範囲は業界や業種によって基準が異なりますが、原則は以下の4点に当てはまる従業員を指します。
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
- 上記のような重要な責任と権限を有していること
- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあること
- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
ちなみに会社によっては、就業規則で管理監督者にも代休取得を認める場合もあるため、今一度自分の会社の就業規則を確認しておきましょう。
従業員が欠勤時に無断で代休を振休処理にした
従業員が欠勤している際に、無断で代休を振休処理にするとトラブルになります。
休日出勤や振休・代休が認められるのは、基本的に使用者(会社)と労働者の間で相互に承諾があった場合だけ。
「割増賃金を払いたくないから」などの理由で、授業員に無断で代休を振休に変更すると、トラブルになります。
振休・代休で労働基準法違反になり得る事例

振休・代休の誤った運用を通じて、労働基準法違反で罰せられる可能性も考えられます。
「知らなかった」で済まされないので、続いて振休・代休で労働基準法違反になり得る事例を紹介しましょう。
- 代休なのに割増賃金を支払わなかった
- 振休なのに休日を取得させなかった
代休なのに割増賃金を支払わなかった
まずは、法定休日に代休扱いで休日出勤したのに、割増賃金を支払わなかった場合です。
労働基準法37条では「時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない」との規定が存在します。
労働基準法違反として未払い賃金の支払いを命じられる可能性があるのが、法定休日に代休扱いで労働させたのに、35%以上の割増賃金を支払わなかった場合です。
裁判例として、割増賃金を払わなかったのが理由で700万円以上の支払いが命じられた事例も。
「割増賃金を支払わなくても、後で払えばいいでしょ」と長期間放置していた場合、多額の賃金を支払う可能性があります。
割増賃金が発生した場合は、必ず期日内に支払うようにしましょう。
振休なのに休日を取得させなかった
続いて、振休を取得して休日出勤したのに関わらず、休日を取得させなかった場合です。
代休は休日を与える義務は存在しない(割増賃金の支払いで足りる)ですが、振休は労働基準法上、必ず代わりの休日を与える必要があります。
法律上の消滅時効である2年以内に与えれば良いとされていますが、基本は休日出勤日の直前直後に与えることが望ましいとされます。
振休・代休の違いを正しく理解して運用しよう

振休・代休の違いは、理解できましたでしょうか。
労働基準法などの法律にも関わる分野なので、うっかりミスで会社に多大な損害を与える可能性もあります。
正しい理解をして、適切に運用できるように日々勉強しましょう。



コメント